前回、「胃癌も生活習慣病」であり、食事・喫煙・飲酒などの影響が胃粘膜細胞のDNAを傷つけ、親の代からの段階を経て発癌に至るとお話ししました。今回は、胃粘膜細胞のDNAが傷つくようなときの症状を自覚できるのか、癌発見の契機になるような症状は特定できるのか、また、病名の告知はどのようになされ、告知の意義は生かされているかなどについて、319人の会員さんに伺った結果をまとめてみましょう。
病気発見の体調ときっかけ
自分の健康は自分で守る
まず、病気が発見されたとき、体調が正常だった人は155名(48.6%)と半数近くおり、少し異常を感じていた人は118名(37%)、体調不良だった人は46名(14.4%)でした。この中で、受診のきっかけが吐血・下血などで緊急を要した人は、11名(3.4%)に過ぎません(図1)。
この人たちと、体調不良だった人を除くと、80%以上の人たちは、ほとんど症状のない状態で胃癌を発見されているのです。
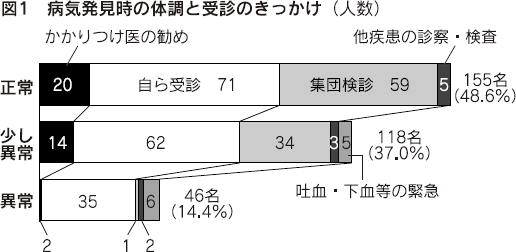
集団検診による受診は、若年(55歳以下)の無症状の男性や、軽度有症状の女性の病気発見に大きな役割を果たしています。また、会社などの集団検診でなく自分の意志で受診した人が168名(52.7%)と半数以上を占めるのは、自分の健康は自分で守ろうという意識の高さを表し、日本における胃癌の早期発見・早期治療による死亡率の低下が実現されてきた実態を、如実に物語る結果と考えられます。
しかし、日本国民の悪性腫瘍全体の罹病率は増えており、発癌予防のための生活習慣の改善がさらに重要になっています。罹病率の増加には、高齢者の増加が関与しているのも事実ですが、肺癌や大腸癌の急激な増加も大きな要因です。
30%が0%に
発癌の原因の第1位は食事で、全癌発生の50%、第2位は喫煙で30%、残りの20%が感染(ウイルスなど)、紫外線、放射線、特定の化学物質などです。
ここで重要なことは、人が何かを食べて生きている以上、食事要因を「0」にすることは不可能で、例えば、胃癌を減らすといわれている食べ物は、偏ると大腸癌や他の消化器癌を増やす可能性が現れたりします。しかし、禁煙により「0」にできるタバコは、最大の「予防できる発癌要因」であるといえるのです。
有名なユタ州の統計では、全米の癌発生率を1とした場合、禁煙を教義とするモルモン教徒の多いソルトレークシティーの発癌率は0.7であり、正確に30%少ないのです。
表1の胃癌による死亡の危険度が、喫煙者は非喫煙者より、男性で1.5倍、女性で1.2倍高いことも注目すべきことであり、胃癌の罹患率を低下させ、死亡率を下げる効果的な方法の一つとして禁煙が挙げられるわけです。

当然、すでに癌にかかった人の「再発予防策」の第一にも挙げられるべきでしょう。
告知の実態とその影響
告知は家族と一緒に
告知は、「本人」と「本人と家族が一緒」を合わせますと、90%以上の方に行われています。家族だけへの告知は6.3%(男性5.8%、女性7.1%)に過ぎません(表2)。
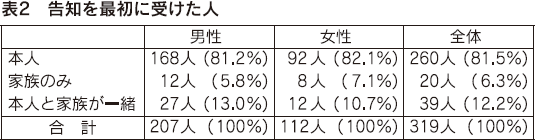
本会で13年前に行った調査では約60%の告知率でしたので、大幅に増えています。なお、3年前の癌の告知に関する「200人アンケート」(本紙235/237号)とはほぼ同率でした。
これは、この10年の間に、胃癌が治りやすくなり、医療者側も「手術さえすれば治せます」といいやすく、患者さん側にも、最近は、ポリープや良性潰瘍での胃切除は少ないという認識があるためでしょう。
しかし、告知の目的は「患者の癒し」にあり、3年前の同アンケートで92.6%の方が望んでいた「告知は自分と家族と一緒に」は、今回の結果を見ても、全く実現されていません。これは「告知至上主義」が医療者側に都合良く解釈されていることの表れであり、根治不能の胃癌でも告知を望む患者さんが80%を超え、「告知の質」が問われる時代に、医療者側の対応が十分になされていないことを物語るものでしょう。
今回の調査でも、告知を受けたときの心境は、冷静に受け止められた人が全体で58.3%(男性62.3%、女性50.9%)に対し、ショックを受けた人も41.4%(男性37.2%、女性49.1%)に及び、約半数の人は冷静ではいられないようです。
その悩みや不安は多岐にわたり、もっとも多かった回答は「家族のこと」、次に「再発・転移・進行度」、「術後の生活・後遺症」、「死への恐怖」と続いています(表3)。
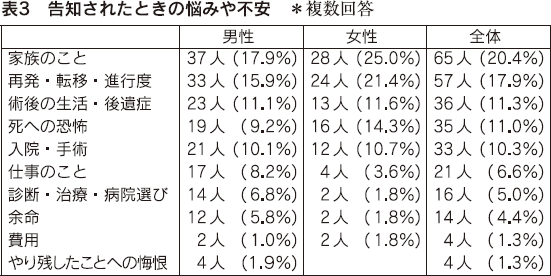
これらの悩みや不安に対し、インフォームド・コンセントやセカンドオピニオンはどのように利用されているか、次回に分析してみましょう。
